2011�N3��11���ɔ������������{��k�Ёi���k�n�������m���n�k�j�ɂ��
�S���Ȃ�ꂽ���X�̂��������F��ƂƂ��ɁA
��Ў҂̊F�l�ɐS��肨�������\���グ�܂��B
8���̒�����
�i��������� ���k��w�������}���āj
�i��������ē����j�\��̌��A�ȉ��̂Ƃ���J�Â������܂��B
�o�ȗ\��̕��́A���A�����肢���܂��i�����A�ȏ����̂��߁j�B
�����@���F2015�N8��10���i���j19���`20��30��
���e�[�}�F�u��v�r�o���̍팸�ڕW���l����v
�����@�e�F�Ē��V�A�AEU�A�u���W���A���L�V�R�A�؍��ɑ����A���{���{�������������\�������ƂŁA��v�r�o���̍팸�ڕW���A�قڏo���낢�܂����B���� �����ׂ�Ƃǂ�Ȃ��Ƃ������Ă���̂ł��傤���B���Y�e�[�}�̑��l�ҁA������ ��� �i������ ���ス��j ���k��w ���k�A�W�A�����Z���^�[�������炨�b���������A���̌�A���R�ɋc�_�������Ǝv���܂��B
���u�t�Љ�F�@http://www.cneas.tohoku.ac.jp/labs/china/asuka/
����@��F�n���E�l�Ԋ��t�H�[�����i���O�j
�ȉ��̍Â��͏I�����Ă��܂��B
JFEJ����
�i��������ē����j���Y�t�̑�����ȗ����ߓ��i�U���P���j�A����E��������J�Â��A���N�x����Q�N�Ԃ̖����̐������܂�܂����B
�Ȃ��A�����͈ϔC��o�Ȃ����킹�ĂQ�U���̏o�Ȃ�����A�芼�ɂ��A�����������葫�������Ă���܂��B
������ �i���@������JFEJ �ł̖�E�j
���� �N �������
�� �N�� ���{�_�ƐV���������
���B���q NHK�������
���� �~ �ǔ��V���������
���� �� �t���[�����X
��]���O �_�C�������h��
���R�j �R�ƌk�J��
�ݏ�S�q �t���[�����X
���c �� �W�p�ЃC���^�[�i�V���i��
��� �O �G�l���M�[�W���[�i����
�c���` �����V��
������a�q NHK
���c����q �t���[�����X
���ؐL�i �����@�K�o��
�R��a�Y �����H�ƐV��
�i�ȏ�P�T�l �\�����j
����
�������Y �G�l���M�[�W���[�i����
�g�c���G �t���[�����X
�i�ȏ�Q�l�A�\�����j
�Ȃ�����^������̊J�Ïڍׂ͎��̂Ƃ���B
�� ���@2015�N6��1���i���j19���`20��45��
����@ 19���`19��25��
���� 19��30���`20��45��
����u�t�@�@���N�����i���{�_�ƐV���j
����e�[�}�@�u�₹�ׂ�y��A���E�̔_�n�ٕς�`����v
�� ���@GEF�~�[�e�B���O�X�y�[�X�i���O�j
5���̒�����
�i�����\�E�q���Ód�͑�\������В����}���āj
�i��������ē����j
�ȉ��̒ʂ��������J�Â������܂��B
�������̕��̂��߁A�Q�X�g�̂��s���ɍ��킹�ċ}���匈�܂�܂����B
���������������B
���o�Ȃ̕��́A�������̏����̂��߁A�K��JFEJ�����ǂɂ��A�����������B
�����@���@2015�N5��22���i���j18�����i���邢��19���j�`
����@���@��ʍ��c�@�l�n���E�l�Ԋ��t�H�[�����~�[�e�B���O�X�y�[�X
�i�䓌�摠�O3-17-3���O�C���e���W�F���g�r��8�K�j
���Q�X�g�@�����\�E�q�厁�i��Ód�� ��\������В��j
�����@�e�@����A�G�l���M�[�~�b�N�X�̌��Ă��o����܂������A����ɑ���Đ��\�G�l���M�[�̗��ꂩ��̂��ӌ��Ȃǂ𒆐S�ɂ��b���f���\��ł��B
http://aipower.co.jp/about.html
������Б�a��X��\�Ј�
�W�U�P�W���p��������Б�\������
�v���W�F�N�g��Ê�����Б�\�����
���{�n�������g��������
NPO�@�l�܂��Â���쑽������
��ʎВc�@�l�ӂ����܉�c����
��ʎВc�@�l��Î��R�G�l���M�[�@�\����
������u�b�n�o21�Ɍ����A��Y�f�Љ��������Z���l����v
�i��������ē����j
3���J�Â̕���ɂ��ē��ł��B
���@���F2015�N3��31���i�j�@19���`20��30��
��@���F�n����l�Ԋ��t�H�[�����~�[�e�B���O�X�y�[�X
�Q�X�g�F�{�� �� ���i�O�䕨�Y�헪�������O���[���E�C�m�x�[�V�������Ɛ헪�������t�F���[�j
��N���\���ꂽIPCC��5���]���i�������j�����������ɁA�J�[�{���o�W�F�b�g�i�Y�f�r�o�g�j�̋c�_�������ɂȂ��Ă��܂����B
CCS�i��_���Y�f�n�������j�����ڂ���A�܂�9���̋C��T�~�b�g�i�m�x�j�̑O�ォ��A���Z�@�ւ̖������d������A���ΔR���Y�Ƃ��炨���������グ����Z�@�ցA�N������̗�Ȃǂ��A�C�O���f�B�A�͕��Ă��܂��B
COP20�i2014�N12���j�ł́ACOP21�̌��e�L�X�g�̈Ă̒��ŁA�J�[�{���v���C�V���O���R�X�g�ʂŌ����I�Ȏ�@�̈�Ƃ��Ċm�F���ׂ����A�Ƃ����ӌ������グ���Ă��܂��B
�ɘa���K����ɁA�\���Ȃ��������悤�ɂ��邱�ƂŊe�����Ƃ̑���㉟�����悤�ƁA�l�X�ȓ��������E�Ő��܂�Ă��܂��B
�r�o�ʎ�����͂��߂Ƃ����Y�f���Z�ɂ����������g�݁A���E�̋��Z����A�C��ϓ����ɖ��邢�{����������b������Ă��������Ɠ����ɁA�c�_�̎��Ԃ�݂��܂��B
������u���g���w�K����x���Z�������ɕ����v
2015�N�ŏ��̕���ł��B
�����@2015�N2��17���i�j19���`20�����\��
�ꏊ�@GEF�~�[�e�B���O�X�y�[�X�i���O�j
�u�t�@�Z�@�����@���i�������������������j
�e�[�}�@���g���u�K����v���Z�������ɕ���
���N���Ƀp���ŊJ�Â���鍑�A�C��ϓ��g�g�ݏ���21 �����c�i�b�n�o 21�j�Œn�����g���ɔ����C��ϓ��ɑ���u�ɘa��v�i�������ʃK�X�팸�j���_�c����܂��B
����ŁA�����ł͍�N���������W�����J�Ȃlj��g���̉e���Ƃ݂����Q���[�������Ă���A�ǂ��u�K���v���ׂ����ɊS���W�܂��Ă��܂��B
���̂��ߊ��Ȃ́u�������R�c��C��ϓ��e���]�������ψ���v�͍�N�W������K����̐R�c���d�ˁA����20���A�u�킪���ɂ�����C��ϓ��e���Ƃ��̃��X�N�]���Ɋւ���ƍ���̉ۑ�v�\���܂����B
���{�I�ȑ�Ƃ��Ċɘa��͏d�v�ł����A��������S�ɒ�������K����ɒ��ڂł��B
�]�������ψ���̏Z�����ψ����i�������������������j�ɉ��g���̉e���Ƒ�ɂ��Ęb���Ă��炢�܂��B
2014�H�J�Ấu���W���[�i���X�g�u���v
���ʐ^�͑�1��̖͗l
�y�ȉ��A�J�×v�|���c���܂��z
������ǂ�����������̃W���[�i���X�g���Q������u���{���W���[�i���X�g�̉�v �́A���̏H�A���W���[�i���X�g�u�����J�Â��܂��B���R�̂��炵����ی�̕K�v����`�������B�O���[�o���Ȓn�������Ɍx����炵�����B��Ƃ̊� �ی슈�����Љ�ɓ`�������B����Ȏ��ɕK�v�ƂȂ�u���H�I�Ȏ�ށv�u�`����Z�p�v���u�`�A���K��ʂ��Ċw�ׂ鑍���I�ȍu���ł��B��ތo���̖L�x�ȃW���[�i ���X�g���u�t�߂܂��B�y�����w�тȂ���A���Ȃ������W���[�i���X�g�Ƃ��Ă̑������X�^�[�g���܂��H
��ÁF���{���W���[�i���X�g�̉����́F��ʍ��c�@�l �n���E�l�Ԋ��t�H�[����
�@�@�@�n�����p�[�g�i�[�V�b�v�v���U(GEOC)
�`���VPDF���_�E�����[�h�ł��܂��B
�y�u�`�z
| 09/17 |
���W���[�i���Y���ւ̏��ҁi���_�j | �����V���ҏW�ψ� �|�� �h�� |
| 09/24 | �Ȋw�̖ڂœ`����� | �����V���Ȋw�����ҏW�ψ� �c�� �` |
| 10/01 | �����ނ̋Z�p | �ǔ��V���ҏW�ψ� ���� �~ |
|
10/08 |
�f�����f�B�A�œ`���� | �m�g�j�v���f���[�T�[ ���B ���q |
| 10/15 | �����Ǝ��R�ی�̕��� �i�t�B�[���h���[�N�̏����u���j |
���{���R�ی싦�� ���R ���� |
| 10/22 |
�Q���̂�炶�ŏ��� | ���^�W���[�i���X�g ���� �N |
| 10/29 |
�o�Ń��f�B�A�̓`���� | �R�Ɵ�J�� ���R �j �_�C�������h�� ��]�� �O |
| 11/05 |
�H�Ɣ_��`���� | ���{�_�ƐV���L�� �� �N�� |
| 11/12 |
�t���[���C�^�[�̐����c��헪 | �t���[�����X ���� �� |
| 11/19 |
�ҏW�Ō�����A�ǂ܂��� | �W�p�ЃC���^�[�i�V���i�� ���c �� |
| 11/26 |
���H�I�A�L���쐬�u���i�܂Ƃ߁j | �����̍u�t�ɂ���i�̍��] |
�����F��L�̓����Ŗ��T���j���A18�F30�`20�F30
�Q����p�F���ɂĂ��������܂��B
�@�@�@��ʁF11 �ꊇ�����@16,500�~�i1,500�~/ ��j
�@�@�@�@�@�@�P�u������u�̏ꍇ�@2,000�~/ ��
�@�@�@���{���W���[�i���X�g�̉����F500�~/ ��
�@�@�@�����\�����ݑ����̏ꍇ�A�撅���ƂȂ�܂��B��������ꍇ�͂��A���������グ�܂��B�@
����F9/17�F90���C9/24�`11/26�F�e��40��
�@�@�@���t�B�[���h���[�N�i���L�́u���K�v�j��p�͕ʓr������܂��B
�@�@�@���̎����������p�̕��͎�t�ł��m�点���������B
���F�n�����p�[�g�i�[�V�b�v�v���U�iGEOC�j
�@�@�@��150-0001 �����s�a�J��_�{�O5-53-70 ���A��w1F
�@�@�@JR�a�J�w���� �܂��� �������g���\�Q��B2 �o�����p
�\����F���L�̐\���t�H�[������o�^�ł��܂��B
�@�@�@https://ssl.form-mailer.jp/fms/95dfeac5314626�@�@
�@�@�@FAX �F03-5825-9737�CE-mail�Fjfej.seminar��gmail.com�@(���Ɂ�������)
�����L�����������܂����l���́A���㓯��̂��ē��Ɍ����Ċ��p�����Ă����������Ƃ�����܂��B
���Z�~�i�[�̖͗l���A����̃z�[���y�[�W���Ɍf�ڂ��邱�Ƃ��������܂��̂ŁA���������������B
�y���K�z
���R���ꂳ��i���{���R�ی싦��j�ƕ����I
�������猩�鎩�R�ی�^���̗��j�̌��c�A�[
10/18�i�y�j�`19�i���j���{�̎��R�ی�^���͔�������͂��܂����ƌ����Ă��܂��B�Â��͐��͔��d�p�̃_���v��ɂ���Ĕ������������v�̊�@�ɂ��炳��A�������͐��ʂ��グ���� �m���Ɏ搅����Ă��܂����B���̌���c�т��錧���J���̒��f�A�I�[�o�[���[�X���ƃS�~�����A��^����}�C�J�[�K���A�ؓ��Ƃ��̊Ǘ����A�r���p�C�v���C ���ݒu���ȂǂŒ��ڂ���A�ŋ߂ł̓N�}�ɂ��l�g���̂�V�J�̐H�Q���ɉ����A���˔\�������뜜����Ă��܂��B���̔�����������Ɓi����͔������G�� �A�j�́A���{�̎��R�ی�^���̗��j���T�ς��A�̊������D�̋@��Ƃ����܂��B���K�ȎR�����Ɉꔑ���Ȃ���A�����Ղ�Ƃ��b�����Ԃ�݂��A���ԓI�ɂ��� �͓I�ɂ��]�T����v��ł��B���r�����łȂ����ł����Ђ��Q�����������B
�����i�\��j
�������`�Q�n���Еi���̑吴���܂ł̓o�X�ňړ��i��4 ���ԁj�B
�吴�������̊}���g�Y����ɁA�V���[�g�C���^�r���[�B
�吴���`��m���x�e���`����`�O�����`�������܂ł����������Ė�R���ԁB
�������q���b�e�h���B��͏����̎x�z�l
��������̗��j�C���^�r���[�B
10�^19�i���j
��]�����`�������`�O�����`��m���`�i�����o�R�j�`�吴���i�k���Ŗ�Q���ԁj�B
���̌�A�吴������o�X�ŋA���B
�������A��ʁA�\�����@���̏ڍׂ͌���A�{�T�C�g�ihttp://www.jfej.org/�j�ɂĔ��\�B
���R ���� ��
1958�N���܂�B�����̃R���T�x�[�V���j�X�g�i�ۑS�����Ɓj�Ƃ��Ē�������B���_�R�n�i�X�E�H�c���j�┒�ہi����E�Ί_���j�A�ԒJ�̐X�i�Q�n���j�Ƃ������M�d �Ȏ��R���J���̍r�g�������Ă��������ł͂Ȃ��A���R�ی�n��̊g�����{�ő�̎��R�ی�c�̂̊��^�c�ɂ����ڊւ��A���{�̎��R�ی�^���̗��j��]�� �_������ő̌�����Ă��܂��B
�L��ƕ��f�B�A�̃V���|�W�E��
2014�N9��17������̘A���u���ɐ旧���A�ȉ��̂Ƃ���V���|�W�E�����J�Â��܂����B
�����e
�u�L��ƕ��f�B�A�̃V���|�W�E�� �v
�L��ɂƂ��ă��f�B�A�́A�ǂ��f���Ă���̂��H
���f�B�A�ɂƂ��Ċ�ƍL��Ƃ͂ǂ�ȑ��݂Ȃ̂��H
���݂��̃z���l���Ԃ������A�L��}���ƕ��鑤�ƂɐV���ȐM���W����������B
���{���W���[�i���X�g�̉�iJFEJ�j����旧�āA��Â���h���I���n�V���|�W�E���B
���L�p�l���X�g
�Ζ��A���Z�p�����S�����i�O�L���j ���܋g����
�L�����i���j�����i�������S�� �R���X�V��
�i�Ɓj������i�@�\�ږ�i��NEC�L�j �ؓ��Ǝ�
��JFEJ���p�l���X�g
�����H�ƐV���И_���ψ� �R��a�Y��
�����V���ЉȊw�����ҏW�ψ� �c���`��
�t���[�����X���C�^�[ ��������
���i��
�i���j�G�l���M�[�W���[�i���Б�\����� �������Y��
�������F9��10���i���j18��30�� �` 20��30��
���ꏊ�F�n�����p�[�g�i�[�V�b�v�v���U�iGEOC�j
�@�@�@�@�a�J��_�{�O5�|53�|70�@���A��w�r��1F
���Q����F500�~
����y�ѓ��ʕ���
���@����2014�N6��18���i���j����@19���`20���i�����A�u��40���{���^20���j
�����
����y�ї�����J����A����25�N�x�����A����v�y��26�N�x�\�Z�����F����܂����B
��ɍ����~�����đI�i2���ځj�B������2����サ�A�ݏ�S�q���Ƒ�]���O��������邱�ƂƂȂ�܂����B
�V�N�x�̎��ƂƂ��āA���H�̊��W���[�i���Y���u���J�ÂȂǂ��c�_����܂����B
�����
�u�@�t���b������I�q���i�������������t�F���[�j
�e�[�}�� �uIPCC��5���]�����̊T�v�ƃV�i���I �@��3��ƕ���𒆐S�Ɂv
���@�e���{�N�S���ɔ��\���ꂽIPCC��R��ƕ�����Łu�G�l���M�[�V�X�e���v�̏͂̎厷�M�҂߂��b������I�q�E�Ɨ��s���@�l�������������Љ���V�X�e�������Z���^�[�E�t�F���[����A���̊T �v�Ȃǂɂ��Ă��b�����������܂����B

�u�����C�u�����[�v�����@
��Q�����@���q���o���C���^�r���[
JFEJ�ł́A�u�����C�u�����[�v���ƂƂ��āA�ȉ��̃C���^�r���[���J�Â������܂��B �u�����C�u�����[�v�́A���ی�E�ۑS�̑����Ŋ���A���{�̊����̗��j�I�،��҂̕��X�ɁA���\�N�ɂ킽�邻�ꂼ��̎��g�݂ɂ��Ă̂��b�� ���������A�u���{�̊����̗��j�v�Ƃ��āA�f���A�����Ȃǂ̌`�ł��̋L�^���c�����Ƃ������݂ł��B
���܂��܂Ȋ��ی�^���̑����Ŋ���Ă����l�������I�ɂ��������āA������J���Ă��b�����������A������܂Ƃ߂��Ƃ�i�߂Ă����܂��B
���ڍׂ͓Y�t���������������B��PDF�t�@�C�����_ �E�����[�h�ł��܂���
��Q��́A�����_��̋��q���o���ł��B
�����F�@2��13���i�j�@�P�W�F�R�O�`�Q�O�F�R�O
�J�Ïꏊ�F�@�A�����5�K�@501����
�@�@�i�����s���c��_�c�x�͑�3-2-11�j
�Q����F�@����F�����@�����F�P�O�O�O�~
����25�N�x�n���������������
���J�V���|�W�E���@���R�̌b�݁u���Ԍn�T�[ �r�X�v���ǂ����邩
��ÁF�� �{���W���[�i���X�g�̉�i�i�e�d�i�j
���́F����c���m�^�n���E�l�Ԋ��t�H�[����
�@2010�N�̐������l������10�����c �iCOP10�j�����������ɁA��ʂɂ��������m����悤�ɂȂ����u���Ԍn�T�[�r�X�v�Ƃ����V�����T�O�B�u���Ԍn���琶�܂�邳�܂��܂Ȏ��R��������l �Ԃ����b���Ă���v�Ƃ����A���̐V�����l�������A�W���[�i���Y���͂ǂ̂悤�ɓ`���Ă����悢�̂ł��傤���B
�@���{���W���[�i���X�g�̉�iJFEJ�j�ł́A�n��������̏������āA2011�N����u���Ԍn�T�[�r�X���ǂ����邩�v���e�[�}�ɁA��ށE���� �𑱂��A�ߋ��Q��̃V���|�W�E���Ȃǂ�ʂ��Ċ��������Ă��܂����B����͂��̑��܂Ƃ߂Ƃ��āA�V���A�e���r�A�G���A�E�F�u�ȂNJe���f�B�A�Ŏ��H���Ă� ����ޕ̕Ɛ��ʂ��L�����L���邽�߂ɁA���J�V���|�W�E�����J�Â������܂��B
�J�����F2014�N�P��22���i���j
�@�@�@�@�@�ߌ�V���` �i�U������t�j
�J�Ïꏊ�F���{�L�҃N���u����c��
�� �� ��F�T�O�O�~�iJFEJ����͖����j
�y�v���O�����z
�J�Â������@�@���� �~�i�ǔ��V���^JFEJ��j
����ފ�����
���u�L�@�_�ƂƏz�Љ�̎����@�`���쒬���Ɂ`�v�@
�� �N���i���{�_�ƐV���^JFEJ����j
�@��������L�@�_�ƂɎ��g�݁A�_�ƌ��C�Ҏ����_�Ǝґ�w�A�A�_�����Z�̍u�t�A�T�|�[�g�Ȃǂ��肪���Ă������쒬�̋��q���o����B����܂łɁA���� �̐l�тƂ̎����ʂ��āA�L�@�_�ƂƏz�^�Љ�̎����ɐs�͂��Ă����������Љ�܂��B
���u�f�����f�B�A�œ`����g���Ԍn�T�[�r�X�h�`�g�߂Ȗ��Ƃ��čl���� ���߂Ɂ`�v
���B���q�iNHK�v���f���[�T�[�^JFEJ�j
�@2010�N�J�Â�COP10�̍ۂɁA�uSAVE THE FUTURE�@�Ȋw�҃��C�u�v�Ƃ����ԑg��ʂ��āA�g���Ԍn�T�[�r�X�h�Ƃ�������T�O���킩��₷���`�������݂���̒m����ANHK�̔ԑg�u���R���{�� �`�v�V���[�Y�̓W�J�ANHK�G�R�`�����l���i�E�F�u�j��V���Ȃǂ�ʂ��Č����Ă����A��炵�≿�l�ρA�n��Đ��̉ۑ�Ƃ��ē`���邱�Ƃ̑�������`���� �܂��B
���u�������l���̂܂��Â���������v
���� �N�i�W���[�i���X�g�^JFEJ�����j
�@�q�[�g�A�C�����h�A�A�����M�[�l���̑����A��C�����B�s�s�����ɐ������邱���R�̖�������Ƃ��āA�������l���̂܂��Â��肪���B�Ŏn�܂��Ă���B �܂��Â���̊ϓ_����A�������l��������o���ƍ���̉\����������܂��B
���p�l���f�B�X�J�b�V������
���u���Ԍn�T�[�r�X�̕�@�@�`�����여����Ɂ`�v
�i��i�s�F���c ���i�W�p�ЃC���^�[�i�V���i���^JFEJ����j
�p�l���[�F�� �N���i���{�_�ƐV���^JFEJ����j
�@�@�@�@�@���B���q�iNHK�v���f���[�T�[�^JFEJ�j
�@�@�@�@�@���� �N�i�W���[�i���X�g�^JFEJ�����j
�������@�� ���i����c���m�m���j
�`���V���_�E�����[�h�ł��܂��i�J�n�������V���ɕύX���ꂽ���Ƃ����f���� �Ă��܂���j
���o�c�e�t�@�C���͂����灄�@���v�������t�@�C���͂����灄
�u�����C�u�����[�v���Ɓ@��P�����
�{�e �� ���C���^�r���[
�@���{ ���W���[�i���X�g�̉�́A�{�N�x���u�����C�u�����[�v�v���W�F�N�g���A�����グ�܂����B
�@���70�N�A���{�̊����́A��㍂ �x�o�ϐ������̌��Q���A���R�ی�^���A�n�������ȂǂւƍL����܂����B
�@�u�� �����C�u�����[�v�́A���ی�E�ۑS�̑����Ŋ���A���{�̊����̗��j�I�،��҂̕��X�ɁA���\�N�ɂ킽�邻�ꂼ��̎��g�݂ɂ��Ă̂��b������ �����A�u���{�̊����̗��j�v�Ƃ��āA�f���A�����Ȃǂ̌`�ł��̋L�^���c�����Ƃ������݂ł��B
�@�{�N �x���A���܂��܂Ȋ��ی�^���̑����Ŋ���Ă����l�������I�ɂ��������āA������J���Ă��b�����������A������܂Ƃ߂��Ƃ�i�߂Ă������� �v���Ă���܂��B
�@�{�e ���́A���l���喼�_�����ŁAIGES���ې��Ԋw�Z���^�[�̃Z���^�[ ���Ƃ��āA���{�͂������A�u���W���E�A�}�]����C���h�l�V�A�E�{���l�I�̔M�щJ�эĐ��A������h�����������̒���ւ̐A�тȂǁA50�N�ȏ���̊ԁA���E�e�n�ŐX�� ��݂����点�Ă��܂��B
�@���� ���̓y�n�ɐl�̎肪�����Ă��Ȃ�������A���Ƃ��Ƃ͂ǂ̂悤�ȐA���������̂������Ƃ߂�u���ݎ��R�A���v�̗��_�����ƂɁA�{�e���́A���̓y�n�{���̐A�� �ɂ��X�Â����50�N�ȏ�̊ԁA�i�߂Ă��܂����B
�@�� ���A�R�E�P�P�̓����{��k�Јȍ~�́A��Вn�̊��I�����̂܂܊��p���A���I�̂����ɓy�n�{���̎���A���āA�S��150km�ɂ킽��u�X�̖h����v����� �\�z��ł��グ�āA���ۂɐX�Â����i�߂Ă��܂��B
�@���� �{�e���̂���܂ł̎��g�݂̗��j���A�����Ղ�ƌ���Ă��������܂��B
�@�@�@ ���@�@���F�@11��29���i���j�@�P�W�F�R�O�`�Q�O�F �R�O
�@�@�@ �J�Ïꏊ�F�@�W�p�ЃA�l�b�N�X�r���@�WF��c��
�@�@�@ �Q����@�F�@����F�����@�����F1,000�~
2013�N11���̒�� ����
��11��18��(��) �P�W�F�R�O�`
�V���[�Y �u���h�~�̎���h�̊��W���[�i���Y���v��Q��
�u�V�����A���������A�����\�Ȃ܂��Â���̘A�� �w�h���_���Ȓ����h�s�s�I�s�x
�@�@�@�@�@�i�n�E�W���O�g���r���[�����A�n���ЁA2013�N2���`9���A�S14��j���I���āv
�@�@�@�@�@���e�́A�G�l���M�[�E�P�A �i���ÁA���j�E�H�̒n�� �����A�ؑ��s�s�Â���A�Z���A�����̂ɂ�������Ԃ�ٗp�̏�̍č\�z�ł��B
�ꏊ�@��ʍ��c�@�l�n���E�l�Ԋ��t�H�[������c��
�u�t�@�����N
2013 �N10���̒�� ����
��10��24���i�j18�����`
�����ʕ���i�C�ۃL���X�^�[�l�b�g���[�N�Ƃ̋��Âł��B����F�e�c��20���j
�@���e�F�����o�ł��w�ُ�C�ۂƐl�ނ̑I���x�i�p��r�r�b�V���j���e�[�}���A ������s�����B
�@�ꏊ�F��ʍ��c�@�l�n���E�l�Ԋ��t�H�[�����ʎ��i�������g���u�����w�v���3���j
�@
��10��22���i�j18�����`
�� �Ԍn �̕����͂����������Ôg����̓c��ڂ̕���
�@�Q�X�g���⟺���I�iNPO�@�l�c��ڗ������j
�@�ꏊ�F��ʍ��c�@�l�n���E�l�Ԋ��t�H�[������c��


��9��17���i�j18�����`
�@�Q�X�g�����P�V���i���E�����s���ǒ��^���E�i���v�j���R�G�l���M�[���c�����ǒ��j
�@�ߒ��w�����̂̃G�l���M�[�헪�\�\�A�����J�Ɠ����x
(��g�V��): �̓��e���x�[�X�ɁA�s�̉��g������̌`���ߒ��Ȃǂ𒆐S�ɂ��b�����������܂����B
�ꏊ�@��ʍ��c�@�l�n���E�l�Ԋ��t�H�[������c��
���e�@�V���[�Y�u���h�~ �̎���h�̊��W���[�i���Y���v��1��
�u�t�@���c���i�W�p�ЃC���^�[�i�V���i���j
3.11�ȍ~�A�����͐k�Ж��A�G�l�� �M�[���Ɉ��ݍ��܂�A���{�����a���ȍ~�́A���y���ɖ��v������悤�Ɍ����܂��B
���������Ȃ��A����̌��݂̎d����ʂ��Ċ��W���[�i���Y�����l����@��Ƃ������B
��1��́A�ǎҎ��_�́h�������h���t�ŁA����̐푈�j�@���Ă����������ꎁ�̕ҏW��S������10 �N�̍��c�����ł��B
���Ԍn�T�[�r�X�̕� �@�� �ւ��錤��
���{���W���[�i���X�g�̉�ł́A�Ɨ��s���@�l���Đ��ۑS�@�\�n��������̏����ɂ��u���Ԍn�T�[�r�X�̕�@�v�Ɋւ��銈���𑱂��Ă��܂������A ���̂��ё���c���m�Ƌ����� ���i��2�e�j���ł��܂����B�@�i2013�N�R���j
�m�� �� �n�T�[�r�X�̕�@�Ɋւ��錤���ƃZ�~�i�[���i��2�e�j�n
��̍s���N���b�N����Ƃo�c�e�t�@�C���Ń_�E�����[�h�ł��܂��B
�Ȃ��A����P�e�͂��̃y�[�W�����ɃX�N���[�����āA�L��������_�E�����[�h�ł��܂��B

���{���W���[�i���X�g�̉�iJFEJ�j��Á@�V�� �|�W�E��
�W���[�i���Y ���́u���R�̌b�݁v���ǂ��`����̂��H
�| �����여��̐��Ԍn�T�[�r�X�|
�s�n���� ������������Ɓt
���{���W���[�i���X�g�̉�iJFEJ�j�ł́A�n��������̏������Ĉ��N���u���Ԍn�T�[�r�X�������ɕ��邩�v���e�[�} �ɁA�����여����ɁA��ށE�����𑱂��Ă���܂��B
2010 �N�̐������l������10 �����c�i�b�n�o10�j�����������ɁA��ʂɂ��������m����悤�ɂȂ����u���Ԍn�T�[�r�X�v�Ƃ����V�����T�O�B�u���Ԍn���琶�܂�邳�܂��܂Ȏ� �R��������l�Ԃ����b����v�Ƃ������̐V�����l�������A�W���[�i���Y���͂ǂ̂悤�ɓ`���Ă����悢�̂ł��傤���B
JFEJ �́A������̗���Ő��Ԍn�T�[�r�X�����Ă��錤���ҁA�s���g�D�A�����́A�e�Y�Ə]���ҁA�W���[�i���X�g�ȂǁA���܂��܂ȃZ�N�^�[�̕��X�ɂ����͂����� ���Ȃ���A��ށE�����𑱂��ĎQ��܂����B���̌o�ߕƂ��āA�ȉ��̒ʂ�V���|�W�E�����J�Â������܂��B������̏㗬���牺���ɂ����āA���́u���R�̌b �݁v�ɂ��āA���ꂼ��̊����A����܂ł̎��g�݁A���̎̕�@�ɂ��āA�����Ȉӌ������̏�ɂ������Ǝv���Ă���܂��B���Ђ��Q�����������B
������������������������������������������������������������������
�y�v���O�����z�i�h�̗��j
�J�È��A�@���c���i�W�p�Ё^���{���W���[�i���X�g�̉JFEJ����j
��P���@�����쐅���n�̊��ۑS�Ƃ��̕�
�����p�B�i�X�яm���m���j
�o������i���{���R�ی싦��j
�����p�r�i�݂Ȃ��ݒ����ۊ�����O���[�v�@�O���[�v���[�_�[�^ �u�����z�^���̗��v�S���j
��������^���R�j�i�R�ƌk�J�Ё^JFEJ�����j
��Q���@�����여��̎��R�̉��b�ƕ�
���c�@�D�i���R�����u���c�{�Ɓv��\������j
�ːΎl�Y�i���q�ݏZ���q�Ɓj
��������^���@�@���i����c���m�m���^JFEJ����j
��R���@�����여��́u���R�̌b�݁v���ǂ��`���邩�H
���@�@���i����c���m�m���^JFEJ����j
�������I�i�����V���L�ҁ^���Ɨ̒n�����{���ψ��j
���@�N���i���{�_�ƐV���L�ҁ^JFEJ�����j
�y���@���z�@�@�Q�O�P�R�N�P���R�O���i���j�P�W�F�R�O�`�Q�O�F�R�O�i��t�P�W�F�O�O�`�j
�y��@���z�@�@���{�v���X�Z���^�[�r���@�X�K��c��
�@�@�@�@�@�@�@�i�����s���c����K���Q�|�Q�|�P�j
�y������z�@�@�T�O�O�~�iJFEJ����͖����j
������������������������������������������������������������������
����̕��͖����ł����A���������A����̓s����A���O�ɂ��\�����݂����肢���܂��B
���\�����݂�JFEJ�����ǂɃ��[���i�����������������D�������j�܂���FAX�i03-5825-9737�j�ňȉ��̕K�v�����������艺�����B
����ɂȂ莟��A���ߐ�Ƃ������܂��B
���������A�ӂ肪�ȁA�����i�Ζ���^�w�Z�j�A�A����i�d�b�ԍ��A���[���A�h���X�j����
�`���V�i�o�c�e �t�@�C���j���_�E�����[�h�ł��܂��B
������u�m ���E�F�C�̎����\�ȋ��ƂƁA���k�̐��Y�Ƃ̍Đ��v
�ꏊ�@�n���l�Ԋ��t�H�[������
�����{��k�Ђ���̕�����ڎw���A���A�{��̐��Y�W�҂�
�m���E�F�C�̋��Ƃ́A�ŐV�̐��Ԋw�ɗ��r���������Ǘ��^�ł���A
�m���E�F�C�̎����\�ȋ��Ƃɏڂ���Per Christer Lund (PhD) �� <>�i�m���E�F�C���Ȋw�Z���^�[�������A�m���E�F�C��g�ًΖ��j�ɁA�����̋��ƂƁA ���k�Ƃ̂������ɂ��Ă��b�����������܂��B
����
��u�k�Ђƌ���
���́@�@�������́A�ǂ��`�������v
�����F7��9���i���j18��45���`20��30��
�ꏊ�F���c�@�l�n���E�l�Ԋ��t�H�[������c��
�u�t�F���B���q�A������a�q�i�m�g�j�j
���e�F��N��3.11�ȗ��A�m�g�j �̐���v���f���[�T�[�i���B�j�A�f�B���N�^�[�i����j�Ƃ��ĉ����l���A�ǂ�Ȕԑg�����������A�����āA�ǂ�Ȏ育���������������B�̌������Ƃɘb���Ă� �������܂����B
�֘A�T�C�g�F �m�g�j�G�R�`�����l���ihttp://www.nhk.or.jp/eco-channel/�jJFEJ����E���ʕ���
��@���@���c�@�l�n���E�l�Ԋ��t�H�[�����@�~�[�e�B���O���[��
�@�@�@�@http://www.gef.or.jp/access/index.html
������@�@18��30���`18��50��
�����ʕ���@19���`20��30��
�C�k�F�������A�|�������A�������s��
�^�C�g���F�u����20�N�v
���� ��u�������A�� ���\�G�l���M�[�����̉\���v
�s2012�N�x�̕���ɂ��āt���W���[�i���X�g�̉�Ƃ��č��N�x�́A�u�������̂���̕����v�Ɓu�O���[���E�G�R�m�~�[�̌��݁@�w���I�{�Q�O�x�̃e�[�}���v�̂Q�{���Ői�߂����ƍl ���Ă��܂��B�@�@�@�i�S���F�����A���j
���y�������̂���̕����z
�����d�͕�����ꌴ�����̂���P�N�������A���������̂ł̏�����Ƃ��{�i���������ő�ь����̍ĉғ��̐�����Ă��܂��B�����������ō�N���߂āA �m���A���c��A�n�������E������ł��o�����������̓����A�����E�p�F�r�W�l�X�̌����A��Вn�ʼn萁�������ւ̓������܂��B��1��͈ȉ��̂Ƃ���ł��B
�e�[�}�@�u�������A�Đ��\�G�l���M�[�����̉\���v
���@���@�T���W���i�j�ߌ�U�����`
��@���@�n���E�l�Ԋ��t�H�[������c��
�u�t�@���쏃�ꎁ
��������������C�������A�������R�c��n��������ψ��A��Â݂����R�G�l���M�[������ږ�A�ъڑ��́u�������Ă܂ł��ȕ����v�����v���������� ���A�������Đ��\�G�l���M�[�����ψ���ψ��B
��Y�f�V�i���I��������傾���A��N���A���H�̏�Ƃ��āA���������̍Đ��\�G�l���M�[�v�����Â���ɂ������B
��8���̌�����ɐԍ⌛�Y�E�����{�����ψ�������
���Ԍn�T�[�r�X�̕� �@�� �ւ��錤��
���{���W���[�i���X�g�̉�ł́A����23 �N�x�Ɨ��s���@�l���Đ��ۑS�@�\�n��������̏����ɂ��u���Ԍn�T�[�r�X�̕�@�v�Ɋւ��銈���𑱂��Ă��܂������A���̂��ё���c���m�Ƌ����� ���i��P�e�j���ł��܂����B�@�i2012�N�R���j
�m�� �� �n�T�[�r�X�̕�@�Ɋւ��錤���ƃZ�~�i�[���i��P�e�j�n
��̍s���N���b�N����Ƃo�c�e�t�@�C���Ń_�E�����[�h�ł��܂��B
�i2012.05.09�j�@��1��1-4-2�Ŏ��M�ҍZ�{���e�����f����Ă��Ȃ�����������A�o�c�e�t�@�C���������ւ��܂����B
����܂łɂ��łɃ_�E�����[�h�������́A���萔�ł���������x�_�E�����[�h���Ȃ����Ă������������B
�ȉ��ɁA����܂ł̊����L�^���c���܂��B
�Ȃ��A�e����̕��͏�L���ɂ��܂܂�Ă��܂��B
*********************************************************************
�i2011�N�x�n�����������������j
�u���Ԍn�T�[ �r�X���ǂ����邩�v
�`�_�ƁA�������A�G�l���M�[�����
�֘A���ā`
��2012�N�Q��16���ɊJ��
2011�N
�́A���Ԍn�T�[�r�X�Ɗ֘A���[��3�̕���ŁA�]�����N�����BTPP���ɗh�ꂽ�_�ƁA�ЊQ�ƌ������̂����������Ɉ��S���A�����ĔF�������������A��
�����R�G�l��
�M�[�������ڕW�ɂȂ����G�l���M�[��3����ł���B�����3����̐����]���A�ЊQ�A���̂��āA�� �]����]�V�Ȃ�����Ă���B
����܂ł̏c������āA���Ԍn�A��炵�A�Љ�S�̂ւ̉e���ƑΉ�������ʂ���͍�������N�ł� �������B
3����ł̕���ł̎��H�܂��A����̕�������b�������B
�u���Ԍn�T�[�r�X���ǂ����邩�v
�`�_�ƁA�������A�G�l���M�[����Ɗ֘A���ā`
�����F�@2012�N2��16���i�j18:30�|20:30�i��t18:00�`�j
���F�@���{�v���X�Z���^�[�r���X�K���c���i�����s���c����K���Q�̂Q�̂P�j
��Î҈��A
�@���c���i�W�p�ЃC���^�[�i�V���i���@�i�e�dJ��j
��P���@�_�ƁA�������A�G�l��
�M�[�̓]�@�ƕ\ ���\��
�@���@�N���@���{�_�ƐV���@�i���R�f�Ջ���ɗh���_�Ɗ�����̕j
�@���с@���@��ѐV�����c�x�ǒ��@�i�����n�Ɠs����Ȃ��j
�@�|���h��@�����V���ҏW�ψ��@�i��
���ƃG�l���M�[�B����̓]�@�������j
�@�������E�n�����L�ҁ@�i�������j
�@
��
�Q���@�c������āi�S�̓��_�j
�@��
�Ԍn�A��炵�A�Љ�S�̂ւ̉e���ƑΉ�������ʂ���ڎw���āA�����K�v��
����F�@�T�O��
������F�@
�T�O�O�~�i�W�Җ����j
���⍇���͓��{��
�W���[�i���X�g�̉�imail�F�@���������i�������D������ tel�F 03-3813-9735�j
*********************************************************************
2011�N�ĂɊJ�Â����u���Ԍn�T�[�r�X�̕�@�Ɋւ��錤���ƃZ�~�i�[�v������ɂ���
���L�ɋL������B�@�m�������N���b�N����ƃW�����v�n
�@��P��@���Á@����
�@��Q��@�h�J���Âݎ�
�@��R��@�x�c���s��
���ꂼ��̕����_�E�����[�h�ł��܂��B
�u���Ԍn�T�[�r�X�̕�
�����v���W�F�N�g�v
���H�����Łg�V�}�t�N���E�h���@���

���ʃR���J���C�̉�ɂ��A�V�}�t�N���E�̑����_��

�����̕������𐅌��Ƃ��鐼�ʐ�B
�{�Y�p�����̗����K���ŁA�ߔN�͐��������ɂ悭�Ȃ����Ƃ����B
��O���̔w��ɉ͔ȗѐA�����ƒn�悪����B��̌������͖q��

���H�s�������̃V�}�t�N���E�B
�߂�����A�D�y�̓������Ɉڂ����\��

�u�^���`���E�̗���w�v�i�q�����w�z�[���̑O��
���H�E���ʐ여���ނ̎��O����� �J�Ái11/28�j
JFEJ����e��
���{���W���[�i���X�g�̉�Ƒ���c���m�ł́A���N�x�A���Ԍn�T�[�r�X���ꎟ�Y�ƁA���� �w�A�o�ϊw�̂R�̎��_�łƂ炦�A�Ȃǂ�ʂ��ĕ\��������@���A���H�E�������Ă��܂��B
���ʐ�ł̓��ʃR���J���C�̉�̊����́A��L�R�̎��_�ŁA�E��������ΏۂƂ��čœK �Ȃ��̂̈�ƍl���Ă���܂��B
�����ɁATPP�Ȃǂ̎��R�f�Ջ��� ������̔_�ѐ��Y�Ƃ̂�������l����ޗ��Ƃ��Ă��A�S���I�ȉ��l�������̂ƍl���Ă���܂��B
���������ϓ_����A�ȉ��̂���l�̂��b�Ղ��܂��B
������u�q�����{�v
�e�[�}�F�@�uRio�{20�v
�u�@�t�F�@�����d�j���i�O�H�����@���E�G�l���M�[�����{����C�������j
���@���F�@�Q�O�P�P�N11���Q��
�i���j�@�P�W�F�S�T�`
��@���F�@�n���E�l�Ԋ��t�H�[�����~�[�e�B���O���[��
�y11���Q���� ��z
����̕���̃e�[�}�́u���I�{20�v�A�u�t�� �O�H�������E�G�l���M�[�����{����C�������̉����d�j���B
1992�N�Ƀu���W���ŊJ�Â��ꂽ���I�E�T�~�b�g�i���ƊJ���Ɋւ��鍑�A��
�c�j����20���N���L�O���āA���N�i2012�N�j�U
���S�`�U���Ƀ��I�f�W���l�C���ŊJ�Â����̂��u���A�����\�ȊJ����c�i���I�{20�j�v�B��c�ł́A
�@�@20�N�o���ă��I��T�~�b�g�ō��ӂ������Ƃ��ǂꂾ���i�����āA�ǂ�ȉۑ�
���c���Ă��邩
�@�A20�N�o���ĐV���ɏo�Ă����ۑ�ɂ��Ă̘_�c
�@�B���I�錾����20�N�o���āA�V���Ȑ����I�錾
�\�\�����҂���Ă���B
����Ɍ����Ă̓��{�����̏�����ƂƂ��� �́A���{�i�O���ȁA���ȁj�Ǝs�����x��������A�s�����x���ł͊S�����X�e�[�N�z���_�[�����N�V��13���Ɂu���I �{20���������ψ���v��ݗ������B���̎����ǂ��O�H���������������A���̎� ���ǃ����o�[�Ƃ��Ē��S�I�Ɋ������Ă����l���������ł���B
�������́u���I�{20�̒��S�I �e�[�}�̈�̓O���[���E�G�R�m�~�[���v�Ƃ݂�B�O���[���E�G�R�m�~�[�ɂ��Ă̒�`�͌ł܂��Ă��Ȃ����A���܂́i��`�͐摗�肵�āj���ƌo�ς̍D�z�� ��i�߂��̓I�{�����A�_�_�Ƃ�������ɂȂ��Ă���A�Ƃ����B
����ɁA���I�{20�Ɍ������� �{���{�́u���ʕ����ւ̃C���v�b�g�v�ƍ��������ψ���́u��āv�ɂ��Ď����Ɋ�Â��ĉ���A�ϋɓI�Ȋ؍��Ȃǂ̓����A�����W�ҁE�c�̂̓����Ȃǂɂ� �ċ�̓I�Ŏ����ɕx�u�������Ă����������B�i���ӁE���j
�u���Ԍn�T�[�r�X�̕�
��@�Ɋւ��錤���ƃZ�~�i�[�v
�ɂ���
JFEJ�ł͖{�N�x�A�i���j���Đ��ۑS�@�\�̊�������u���Ԍn�T�[�r�X�̕�@�Ɋւ��錤���ƃZ�~�i�[�v�ɂ��ď����������� �����邱�ƂɂȂ�܂����B
����́A�@���Ԍn�T�[�r�X�����R�Ȋw�ƌo�ϊw�ŕ\�����錤���ҁA�A���R�Ɛ��ƁE�Y�ƂƂ̐� �荇����T��E�Ɛl�A�B�����E�����W���[�i���X�g�A�����O�҂̘A�g���d�v�ł��邱�Ƃ���A���̎O��ނ̒S����̔��@�A�g�D�����͂��邽�߂� �������ɂ킽���ĊJ�Â�����̂ł��B
���P�e�Ƃ��āA�����҂��猻��ƓW �]���w�Ԍ������A�����ĂR�`�S����{����\��ł��B
�e������20�����x�ł��̂ŁA�� �S��������͎����ǂ܂ł��₢���킹���������B
�i�������̓s���ɂ��A��R��2�����ɂȂ�܂����j
�@�`��Вn�̐��Ԍn�T�[�r�X�`�@�����̎��_����
���@���F�@7��28���i�j18:30-20:30


�m�c���^�̂o�c�e���_�E�����[
�h
�ł��܂��n
��
���Ԍn�T�[�r�X�̕�@�Ɋւ��錤���ƃZ�~�i�[�@�������3��
�u�l�Ǝ��R�̂������v�]���̉\���Ɖۑ�
����3��ł��B
�E�u���R���ɑ��鋦���ɂ�����u�ꎞ�I�ȓ��Ӂv�̉\���\�A�U���̐����R�Đ����Ɂv�w���Љ�w�����x16��
�i2010�N�j
�E�u�n�c�^�s�������ƃ��[�J���ȋ��I�Ǘ��̑Η������z���邽�߂Ɂv�w���ϗ��w�x�i������w�o�ʼn�E2009�N�j
�E�u�ЂƂ�Љ��l���鎩�R�Đ��\���R�Đ��͂Ȃɂ̍Đ��Ȃ̂��v�w���R�Đ��̂��߂̐������l�����j�^�����O�x�i������w�o�ʼn�E2007�N�j
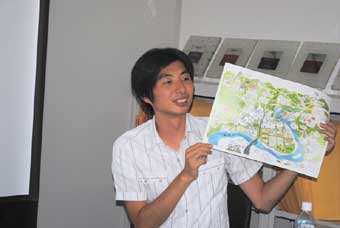
�m�c���^�̂o�c�e���_�E�����[�h�ł��܂��n
��
���Ԍn�T�[�r�X�̕�@�Ɋւ��錤���ƃZ�~�i�[�@�������Q��
�����F�@8��29���i���j18:30-20:30
�}�g��w�u�t�A���������o�āA������w�����i��w�@�_�w�����Ȋw�����ȁj�B
���Ԋw�E�ۑS���Ԋw�i�A���̐����j�̐i���A�A���ƍ����̐����ԑ��ݍ�p�A
�������l���ۑS����ѐ��Ԍn�C���̂��߂̐��Ԋw�I�����Ȃǁj�B
�����Ƃ��āA�w���{�̋A�������x�w�ۑS���Ԋw����-��`�q����i�ς܂Łx
�w�I�I�u�^�N�T�A����-�����ƓK���̐��Ԋw�x�w�}���n�i�o�`�n���h�u�b�N�x�i�����j
�w��݂�����A�T�U�炭���Ӂ|�����Y����̒���x(���Ғ��j
�w���Ԍn��h�点��x�w���R�̊��w�x�i���Ғ��j�w�^�l�͂ǂ����炫�����x
�w�O����n���h�u�b�N�x�i�ďC�j
�w���Ƃ�܁\�\�������l���Ɛ��Ԍn�͗l�x�i��g�W���j�A�V���j
�Q�lURL�F http://www.es.a.u-tokyo.ac.jp/labo/labo_ce.htm


�m�c ���^�̂o�c�e���_�E�����[�h�ł��܂��n
�m2012�N�Q��16����ē��ɖ߂�n
�Ă̌��w���d���H�[�i�� �،��E�ߐ{�����j
http://www.hidenka.net/jtop.htm
�������@2011�N8��28���i���j13���`18������@

�ʐ^�O�A����������Ă���̂���d���H�[��ÎҁE�������V��
����23 �N�x������J��
���ʕ�
��F
�����������̂܂��ẴG�l���M�[���
�ѓc���́A�R��11���ɕ�����ꌴ���Ŗ��炩�ɏd��Ȏ��Ԃ��i�s���Ă���̂ɓK�ȑΉ��������A��������ɕ����̎s���ɕ��ː������𗁂т���Ɏ������o�� ��A���̌�́u���v�v���d�Ȃǂɂ��āA���@�E���d���̑Ή���ᔻ�B�܂��A���̂Ƃ���̐ߓd�L�����y�[���͌����K�v�_�����N���邽�߂̂��̂ŁA���̉Ă� �d�C�͑���邱�ƁA�����ԂɂȂ��炦��Ȃ疳�Ԍ��E���ی���Ԃ̑S���̌����͂܂��~�߂�ׂ��ł��邱�ƂȂǂ��w�E�B����ɁA���łɘV�������Ă��錴���ɂ� �锭�d�䗦��20�N�ȓ��ɕK�R�I�ɉ����邪�A���傤�NJv���I�ɐi�W���Ă��鎩�R�G�l���M�[�Z�p�ւ̒u���������\�ł��邱�ƂȂǂ����܂����B


�V ���ē��F�@�w���s�� �w�x
����c���m�̌����搶���A��
���̏��Ђ̂��ē������������܂����B
*********************************
�w�� �s���w�x�\�@�����ƃG�R���W�[�@�i�������X���@�艿�Q�O�O�O�~�j
���R���R�O����������܂����B
����c���m�����ꂩ�甭�M���Ă������ʂȃ��b�Z�[�W���A�u�� �s���w�v�ɂ���ċ�̓I�ɏœ_�����Ԃ��ƂɂȂ�܂����B
����A���ڒʂ����������A���b�Z�[�W���L����ׂ����͓Y�����������܂��悤���肢���܂��B�u���s���w�v�̑т̋L�����Љ�܂��B
���s�ɍ������@���E�̍ō����Ђ��A�����Ɍ�肩����B
�u���̂��͂߂���v
�����{��k�ЈȌ�A���݁E���ݓI�Ɋg���錻�㕶���ւ̕s�M�E�s���ɑ��āA���߂��Ă���v�z�Ƃ͉����B
�`���̒n�E���s����A���i�́u���ϗ��v�ł͂� ���A�u���R�̒��̐l�ԁv�̑��݂��Ɍ�肩����Ƌ��ɁA
�Y�ƎЉ�̋Ɍ��I�Ȗ������o�������u�����v�̐l�X�����B�����u�F��v�̂��Ƃ��A
����ɂ�����@ �����̃��A���Ȃ���悤�ɂ�������^����B
�Q�O�P�R�N�S���R��
����c���m�@�m���@����
���w�Ȃ��邢�̂��x�o��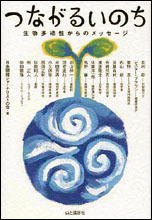
�E�������l��������̊������ʂ��{�ɂȂ�܂����B���{���W���[�i���X�g�̉���A�w�Ȃ��邢�̂��@�������l������̃��b�Z�[ �W�x�i2005�N12��10�����s�A�R�ƌk�J�Ёj�B�������l�����L�[���[�h�ɁA�e�E�̎��ҁE�����l17���̐���������ނ��Ď��^���Ă��܂��B�艿�{ ��1500�~�i�ŕʁj�A�S�����X�Ŕ̔����ł��B
�E�R�ƌk�J�ЃE�F�u�T�C�g�Fhttp://www.yamakei.co.jp/
���M�҂Ȃǂ͂�����ł��m���߂��������B
�i�E�ʐ^�͏���Ȃ��瓯�T�C�g���炢�������܂����B���X�ł̓C�G���[�̑т��ڈ�B�j
�E�Ȃ��������l��������̖͗l�́i���j�n���E�l�Ԋ��t�H�[�����u�O���[�o���l�b�g�v�A�R�ƌk�J�Ёu�R�ƌk�J�v�A�����ʐM�Ёu���E�T
��v�Ɍf�ڂ���܂����B��L���Ђ̌f�ڑΏۂ́u�R�ƌk�J�v�u���E�T��v�A�ڂƏd�����܂������Зp�ɑ啝�ɏ����ւ����Ă��܂��B
�E�u�O���[�o���l�b�g�v�ł͊�Goo�u�������l�����l����v�T�C�g�ł��ǂނ��Ƃ��ł��܂��B
�ihttp://eco.goo.ne.jp/nature/biodiversity/�j
����܂ł̍ŐV��
��
�����L�^�@�F���E�V��
�|�W�E���^�A�W�A���W���[�i���X�g�𗬃Z�~�i�[�^���@�^���ۉ�c�^�o�ŁE��
�֘A�_���@�F���@���u���{�ɂ�������W���[�i���Y���̉ۑ�v���ߋ��A���݂Ɩ������i�p���������j
�u���W���[�i���X�g�̉�v�Ƃ��^
���܂��@�F�{��Webmaster���܂މ���������W�����V�����ЁA�u�����f�B�A�_�v�B
